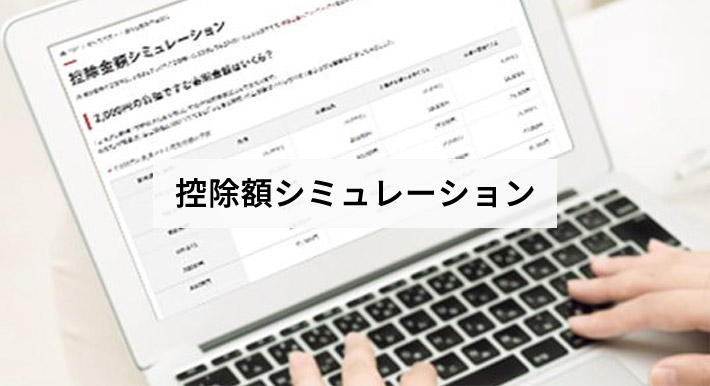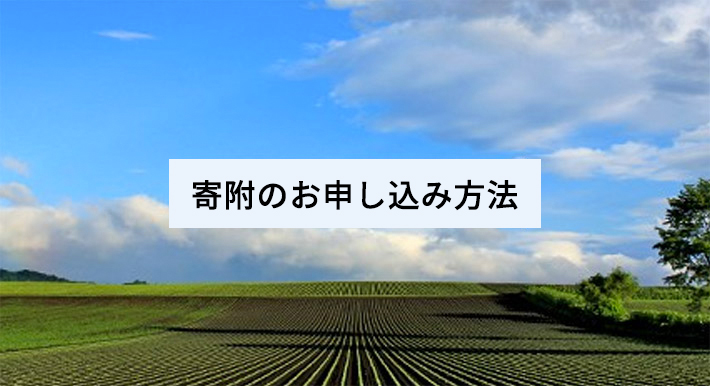新着の返礼品
高評価の返礼品
au PAY ふるさと納税からのお知らせ
- 2024.04.22
- 新たに37自治体の寄附申込みがスタートしました
- 2024.03.15
- 新たに7自治体の寄附申込みがスタートしました
- 2024.03.14
- 【更新】4月のメンテナンスについて
- 2024.02.29
- 3/14(木)01:00~06:30 システムメンテナンスのお知らせ
- 2024.02.22
- 【復旧】au PAYカード支払いがご利用しづらい状況について
- 2024.02.21
- 2/22(木)システムメンテナンスのお知らせ
- 2024.02.15
- 新たに2自治体の寄附申込みがスタートしました



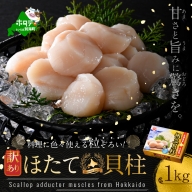


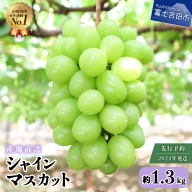
![訳あり 銀鮭 切身 約2kg [宮城東洋 宮城県 気仙沼市 20562683] 鮭 海鮮 規格外 不揃い さけ サケ 鮭切身 シャケ 切り身 冷凍 家庭用 訳アリ おかず 弁当 支援 サーモン 銀鮭切り身 魚 わけあり](https://furusato.wowma.jp/upload/save_image/658630_image_1_s.jpg)


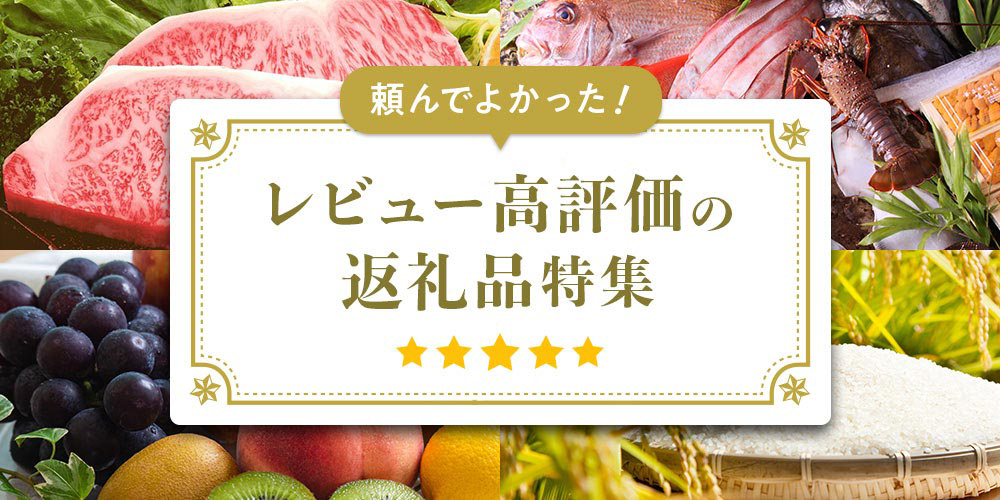









![大人気! 牛タン 厚切り牛タン塩味 1kg (500g×2) [モ~ランド本吉 宮城県 気仙沼市 20562922] 焼肉 牛肉 精肉 牛たん 牛タン塩 牛たん塩 冷凍 BBQ アウトドア バーベキュー 小分け 厚切り タン 牛タン](https://furusato.wowma.jp/upload/save_image/362075_image_1_s.jpg)